
新年あけましておめでとうございます。 この年末は、音楽朗読劇「借りた風景」の翻訳作業の仕上げに追われていました。「明子さんの被爆ピアノ、その記憶とともに」という日本語版の副題が示す通り、広島の原爆で亡くなった河本明子さん…
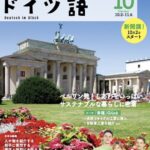
10月から新開講したNHK「しあわせ気分のドイツ語」のテキストに、新しい連載を寄稿しています。テーマは、「ベルリン発、終着駅への旅」。ブランデンブルク門やポツダム広場など、ベルリンの地名にはそこから延びる街道の行き先にち…

小学校の高学年から中学にかけて、鉄道模型に熱中していたことがあります。最初はNゲージから入ったのですが、鉄道模型の完成品は高価です。こんな高いものをしょっちゅうせがまれては困ると両親は思ったようで(笑)、ある時母が横須賀…

先週日曜(3月17日)、早稲田大学交響楽団のベルリン公演がフィルハーモニーで行われました。実に素晴らしかったです。公演が終わってからも聴いた方からの熱い感想が直接的、間接的に届き、いまだに余韻が続いている感じがします。 …

イスラエルとパレスチナを巡る情勢で気の重い日々を過ごしているが、記憶が鮮明なうちに10月9日の出来事のことを書き記しておきたいと思う。 この日の11時前、私はベルリン・フリードリヒシュトラーセ駅前の「キンダートランスポー…

この10月から装いを変えるNHKテレビのドイツ語講座「しあわせ気分のドイツ語」のテキストに半年間の連載記事を担当させていただくことになりました。タイトルは「ドイツ世界遺産プラスアルファ」。ドイツにある51の世界遺産(先月…

先月末、一時帰国を終えて日本からベルリンに戻りました。ウクライナ戦争以降、高騰する飛行機代は悩みの種です。これまではフィンエアを使うことが多かったのですが、今回初めて中東経由のカタール航空を利用しました。そのことを書いて…

4月のベルリンの天気というのは概ねそうなのですが、寒暖差の変化が激しく、なかなか春らしい日がやって来ません。そんな中、先日久々にポカポカ陽気になったので、家族で自転車に乗って出かけることにしました。 まず向かったのは近所…

昨年2月、ブログに「ピアノがやってきた!」という記事を書いたことがある。コロナ禍の最中に、たまたま知人を通じてベルリンのある教会から古いピアノを譲っていただく機会に恵まれ、ゼロからピアノを始めたことを綴った。 あれから1…

大分時間が経ってしまいましたが、夏の思い出を少しブログにまとめておこうと思います。息子の小学校の夏休みを利用して、7月初旬から8月なかばまで2年半ぶりに家族で一時帰国しました。ようやくベルリン・ブランデンブルク国際空港を…

今日6月18日(土)の20時5分から、ドイツの公共放送局Deutschlandfunkにて、ラジオ音楽劇『借りた風景』が放送されます。この作品が完成し、ドイツ全土、さらにインターネットを通じて世界中のリスナーに届けられる…

前回に続いて、フンボルト・フォーラムの展示「ベルリン・グローバル」の後半をご紹介したいと思います。Grenzen(境界)という部屋に足を踏み入れると、床に描かれたベルリンの地図が光で照らし出されました。ベルリンで境界とい…

昨年7月、ベルリンの中心部にフンボルト・フォーラムがオープンしました。かつてのベルリン王宮を再建する形を取りつつ、中身は芸術、文化、学術、教育をテーマとする複合文化施設として新たに誕生したのです。 この中にはプロイセン文…

オクサーナ・リーニフというウクライナ出身の女性指揮者の名前を知ったのは、一昨年の秋のことだった。日頃からお世話になっている音楽愛好家の編集者(仮にAさんとさせていただく)から教えてもらった。「今欧州を中心に活躍の場をどん…

新年あけましておめでとうございます。時間が空いてしまいましたが、前回の続きで、U5に乗ってウンター・デン・リンデン駅から東へ向かいます。 ウンター・デン・リンデンで1つ立ち寄りたいのが、東側のベルリン国立図書館。私がベル…
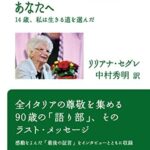
最近発売された岩波書店『世界』2022年1月号で、「世界最大の分散型記念碑――グンター・デムニッヒと仲間たちの『つまずきの石』(前編)」を寄稿しました。このブログでもこれまで何度かご紹介してきましたが、私にとって過去とい…
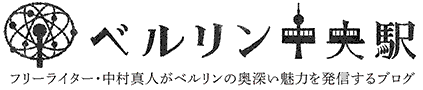

最近のコメント