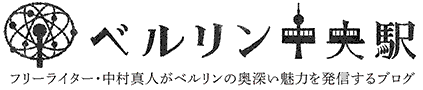神戸大学大学院国際文化学研究科の藤野一夫教授が、『新型コロナ危機に対するドイツの文化施策』に続いて、『パンデミック時代のドイツの文化政策』という連載記事を拙ブログに提供してくださることになりました。その中心テーマとなるのは、藤野氏が「日本の読者にも緊急に紹介する価値がある」と考える、3月31日にドイツ文化政策協会が出した10項目の声明です。初回ではこの10の声明を紹介した上で、最初の2つの声明について藤野氏に解説していただきます。
かなりの長文ですが、非常に刺激的な内容です。「ドイツの文化政策において、目下注目されている政府だけでなく、市民社会セクターのパワーを紹介したい。そして、日独を問わず、なるべく多くの方に『ポストパンデミック』の芸術文化と社会のあり方について問題提起したい」という藤野氏の意思がこもった連載を、ぜひ皆さまにお読みいただけたらと思います。
パンデミック時代のドイツの文化政策(1)
藤野一夫(神戸大学)
はじめに
ドイツの文化政策協会Kulturpolitische Gesellschaftは2020年3月31日に「文化政策は持続的に影響を与えなければらない−コロナ-パンデミック後の文化政策のための10項目」(https://kupoge.de/pressearchiv/pressedok/2020/Kulturpolitik_nach_der_Corona-Pandemie.pdf)を発表した。文化政策協会は非営利の社団法人で、実務家を中心に約3,000人の会員を有し、原則として年会費で運営されている。また、文化政策研究所を併設し、専門研究員による高度な文化政策研究をもとにアドボカシー、コンサルティングを行っている。文化政策協会の季刊誌『kulurpolitische mitteilung』と、2000年以降は連邦政府文化メディア委任官庁(以下BKMと略記)から1億円弱の助成を受けて年鑑『Jahrbuch für Kulturpolitik』を刊行。季刊誌は毎号100ページ、年鑑は500ページに及ぶ。いずれもアクチュアルな文化政策上のテーマをめぐる先端的な論考や討議が掲載され、また年毎の統計やクロニックや文献を網羅している。
「コロナ-パンデミック後の文化政策のための10項目」は文化政策協会のアドボカシー活動の一つであり、会長トビアス・J・クノープリヒ博士の名前で出されている。クノープリヒは、21年間会長を勤めたオリヴァー・シャイト博士の後任として2018年に会長に選出されたが、現職はエアフルト市文化局長。2001年から2010年まで、ザクセン州社会文化連盟事務局長を歴任し、2016年にヒルデスハイム大学に提出した論文「社会文化の綱領諸文と実践諸形式:文化的民主主義としての文化政策Programmformeln und Praxisformen von Soziokultur: Kulturpolitik als kulturelle Demokratie」で博士号を授与された。もとより1976年に発足した文化政策協会は、「社会文化」Soziokulturを首唱する「新しい文化政策」を推進してきたが、クノープリヒはその第三世代とみなしてよい。以下、まず仮訳した10項目を紹介し、順番に適宜コメントや背景の説明を加えてみたい。
コロナ-パンデミック後の文化政策のための10項目
1.文化国家ドイツの文化インフラストラクチャーはシステム上重要である。文化インフラは、経済、社会的なもの、教育、学術と同様の注目を必要とする。加えて文化インフラは、民主主義的議論に著しく貢献し、社会的コンセンサスのさらなる発展と反映のための機会を提供する。
2.連邦、州、市町村は、文化政策の観点から結束しなければならない。最終的に文化政策的に評価されるべきは、いかに連邦主義と補完性を新たに調整して、文化領域において強靭な構造を打ち立てるか、そして市町村が負担過剰にならないことである。連邦主義と補完性(の関係)が、危機から抜け出す道を分断し、特に市町村にとって過重な負担となってはならない。
3.文化施設の法的設置主体である州および市町村は、これらの施設の維持のために配慮しなければならないが、その一方で独立した(フリーの)公益領域は特別な危機に瀕している。この領域は公立と同じ権利において、長期的な救済策が講じられなければならない。
4.一連の危機を保障するための市町村の財政出動は莫大であり、至る所で荷重負担になっている。その際に、とりわけ自発的な自主管理課題が節約努力の照準とされている。適切な助成制度を一定期間持続させるためには、新たな規則の仕掛けや裁量の余地が必要である。このような仕掛けがなければ、橋渡しの仕事(救済策)は、特に施設・機関と事業の被助成者にとって空回りしてしまうからだ。
5.救済のシナリオは持続的に練られなければならない。それは文化施設と文化運営者のレジリエンスを促進しなければならない。ここでは、環境に適合した上演会場の改修と同じく長期的な契約関係が重要であり、助成を受ける運営者側の予備費の蓄えも重要だ。
6.個人的な参加をもっと深めること! ひとり一人の損失経験は個別的なものである。だれもが維持のために尽力できているのは、ボランティアや寄付などの申し出のおかげである。制作者と利用者の間での連帯が至る所で生まれていることが、持ち堪えようとする力を強化している。このことが、危機からの持続的な成果と新たな注目点となりうるだろう。ここで前に進む助けとなっているのは、新しいテクノロジーだけではない。危機の体験が非常に具体的な支援となっている。すなわち、危機の体験が定常性へと変換されうるのである。文化政策的なアピールは、政治に向けられるだけではない。市民社会にも向けられているのだ。わたしたちは「共通のものである危機」を共に克服しなければならない。
7.文化政策は社会構造政策である! この危機は文化の発信者をも変化させる。わたしたちはそのようなことを難民危機において、また他の大災害経験(たとえばエルベ河大洪水)の際にも学んできた。日常に立ち戻るのではない。そうではなく、さまざまな社会テーマ、働き方、ルーティン、諸関係について考え抜き、新たな社会的反響や共感を生み出すこと。すなわち、この危機が一つの認識にならなければならない。
8.コロナ危機の中で、劇場、ミュージアム、フリーランスの音楽家やその他の文化アクターたちは、その観客へのプレゼンテーションとメッセージのために、前代未聞の規模でデジタルメディアを発見した。しばしばインターネットに冷ややかな態度をとり、批判的に対峙してきた文化領域は、その可能性を迅速に、想像力豊かに、また双方向的に利用した。現在、困難な条件のもとでマスターされたことは、今後、芸術・文化機関にとって普通のケースとなるにちがいない。「デジタル時代の文化」はひとつのチャレンジであって、そのためにも、それにふさわしい物質的かつ人的資源が供給されなければならない。
9.文化供給(公演や展示)の長期的な保障は、文化発展計画や重点化施策と結合されなければならない。というのも大切なのは即成栽培ではなく、構造を形成する要素にほかならないからだ。わたしたちは危機からの再生に寄り添わなければならない。そして危機から学び、拡大する危機に、より適切に備えることができるように、探求しなければならない。その際に、応用志向の研究が重要な貢献をなしうる。
10.ミュージアム、図書館、音楽学校、美術学校、市民大学、社会文化センター、自営の劇場、都市地区文化、公共空間のアートなどの文化と文化施設の役割が、定常性の回復において過小評価されてはならない。人々は不安と隔離の月日のあと、お互いに共同体経験に気を配るようになるだろう。こうした力がわたしたちを支える動機づけとなり、わたしたちが喫緊に必要としているエネルギーをも結集するだろう。わたしたちは新たなコンセンサスの形成に文化政策の観点から参画しなければならい。それはまた(社会の)基本方針を刷新するチャンスをも意味しうるのである。
項目ごとの解説
1.文化国家ドイツの文化インフラストラクチャーはシステム上重要である。文化インフラは、経済、社会的なもの、教育、学術と同様の注目を必要とする。加えて文化インフラは、民主主義的議論に著しく貢献し、社会的コンセンサスのさらなる発展と反映のための機会を提供する。
まず、冒頭からドイツを「文化国家」Kulturstaatと呼び、その文化インフラを「システム上重要」systemrelevantと規定しているが、きわめて挑戦的な一文である。その背景の理解のために一寸、歴史を振り返っておきたい。というのも、戦後(西)ドイツの文化政策は、市民社会セクターによる文化的民主主義の形成と成熟のプロセスを経て、はじめて公的に合意されてきたからである。コロナ危機の中で連邦政府の文化支援策が脚光を浴びているが、ドイツの文化政策の主体は、あくまでも州および自治体の住民である。市民社会セクターの厚みを構成する主役(プロタゴニスト、アクター)たちが文化的公共圏を担っているのだ。
19世紀ドイツでは「文化国家」概念は当初、官僚制によって硬直化した法治国家を精神文化によって自由で明朗なものにする、という意味合いで使われた。リベラルなコスモポリタニズムが「文化国家」の精神であり、それは法治国家と矛盾するものではなかった。しかし法治国家が肥大化し、官僚システムの発展が大学の研究・教育の内容にまで干渉するようになると、大学の精神の空洞化を危惧する知識人たちの間から、学問と大学の自治を堅持しようとする動きが強まる。その際に彼らは「文化国家」概念によって精神文化(教育、教養形成、学問、芸術)を護ろうとした。文化国家の概念は1919年のヴァイマル憲法において条文化され、国家からの自由権の保障だけでなく、国家による文化振興が奨励された。
「官僚的君主制が直接役立つ見返りを要求せず、学問と精神の世界に過度に厳しい監督権を行使しないで、学問におしみない援助を与える」。「芸術、学問及びその教授は自由である。国は、これに保護を与え、その奨励に関与する」。(中村美帆「文化国家」、小林真理編『文化政策の現在1 文化政策の思想』、東京大学出版会、36頁以下。拙編著『基礎自治体の文化政策』、水曜社、44頁)。
ところが、この文化国家論が1933年以降、皮肉にも中央政府が文化振興を行う責務と仕組みを正当化する基盤となっていった。ヒトラーの中央集権的文化政策の温床となったのである(拙稿「地域主権の国・ドイツ 文化の分権的形成と文化政策の基礎」、藤野・秋野・フォークト編『地域主権の国 ドイツの文化政策』、美学出版、18頁以下)。こうした過去への反省に立って、戦後のボン基本法では「文化国家」概念は採用されなかった。
けれども2000年代に入ってから、グローバル化に伴う文化領域の市場化への対抗措置として、主に市民社会セクターの側から文化国家条項を基本法に盛り込むべきとの動きが強まってきた。その火付け役となったのは、ドイツ文化評議会Deutscher Kulturratの声明「生存配慮としての文化」(2004年9月29日付 „Kultur als Daseinsvorsorge!“)である。
ドイツ文化評議会は、ドイツ文化政策協会と並んで、市民社会セクターにおける文化政策研究とアドボカシーを中心的に担い、以下の8分野のドイツ文化諸連盟を包括する上部組織である。(ドイツ音楽評議会、演劇・ダンス評議会、ドイツ文学会議、ドイツ美術評議会、建築文化・文化遺産評議会、ドイツ・デザイン評議会、ドイツ・メディア評議会、社会文化・文化教育評議会)。
ドイツ文化評議会は、個々の分野にとって重要な文化政策上の案件全般に関して、連邦、16州、EUの政策および行政の助言機関として信頼され、その目的は、分野を横断する全州的な問題を、あらゆるレベルでの文化政策的な議論に付すことである。年間運営費は1億円強、職員8名、ボランティアスタッフ400名、会員258団体から構成されている。団体が会員の点で、個人を会員とする文化政策協会とは性格が異なる。
ドイツ文化評議会の沿革は、1981年に全州的に重要な文化およびメディア組織と機関に関する、政治的に中立な研究グループとして設立され、1995年公益協会に移行。2002年から文化をテーマとした広報誌『Politik&Kultur』の発行を開始し、2012年から「文化レッドリスト」die Rote Liste Kulturを発表。閉鎖・解散の危機にある劇場、博物館、市民活動団体、協会、プログラム、映画館などを公表している。
難民危機後の2016年にはドイツ文化評議会の提唱で、連邦内務省、厚労省、文化・メディア庁、移民・難民と統合庁が連携して「文化的統合のイニシアチブ」を創設。2017年プロジェクト・オフィス「文化&メディアにおける女性」を創設し、文化・メディア分野における男女同権のための具体的施策の実現を目指している。2018年にはプロジェクト・オフィス「持続可能性&文化」を創設。連邦環境・自然保護省と連携して持続可能な発展のための支援し、自然・環境の持続可能性の議論と文化政策上の論議との橋渡しを行っている。
さて、ドイツ文化評議会は声明文「生存配慮としての文化」において「文化的生存配慮」の概念を論証したあとで、基本法の中に「国家目標としての文化」Staatsziel Kulturを取り入れることを要求している。「基本法における文化の国家規定は、芸術の自由の言明を超えて、ドイツ連邦共和国を文化国家として定義することになるだろう。ドイツ文化評議会の見解では、新たに基本法第20条b項において、国家は文化を保護し、振興すると公式化されるべきであろう」。
このような機運を受けて、2003年に設置されたドイツ連邦議会文化諮問委員会「ドイツにおける文化」は、2007年12月に提出した『最終報告書』の中で、基本法第20条にb項「国家は文化を保護し、振興する」を追加すべきであると勧告した (Deutscher Bundestag(Hrsg.), „Kultur in Deutschland“, Regensburg, 2008, S.89.)。しかしながら、この勧告は、現時点でも連邦議会において採択されておらず、したがって基本法改正は実現していない。終戦から75年、ドイツ統一から30年を閲した2020年に至ってもなお、ドイツ連邦共和国は「文化国家」として自己規定することに慎重な態度を貫いているのである。
ちなみに、5月9日にメルケル首相が行ったテレビ演説「コロナと文化」(https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de)は、「文化支援の課題は、連邦政府による優先順位リストの最上位にある」という明快な声明だった。多くの文化関係者に勇気と希望を与えたが、演説の冒頭は「ドイツは文化の国であり、わたしたちは国中に広がる多様な公演や展示に誇りを持っています」で始まっている。「文化の国」はein Land der Kulturであって、「文化国家」Kulturstaatは一度も使われていない。
これに対し、市民社会セクターに根を張った公益団体である文化政策協会は、ドイツ文化評議会と同様に「文化国家ドイツ」を標榜している。もとより「文化インフラストラクチャー」は、文化施設だけでなく、芸術家、アートマネジャーなどの人的資源、さらに活動や事業を含む包括概念である。ドイツの文化インフラこそが「民主主義的議論に著しく貢献し、社会的コンセンサスのさらなる発展と反映のための機会を提供」してきた、という実績と自負が、文化政策協会のプロタゴニストたちにはある。
戦後ドイツの文化関係者は、芸術文化とその議論を通して民主主義を根付かせ、新しい市民社会の形成と発展に大きく寄与してきた。少なくとも連邦政府としての国家ではなく、ボトムアップ型民主主義の文化運動こそが「文化国家」の実質を形作ってきたのである。
さらに注目すべきは、「文化国家ドイツの文化インフラはシステム上重要である」という自己規定における「システム上重要」の意味である。近年ドイツで耳にすることの多いキーワードであるが、コロナ危機の中でその頻度が高まっている。「システム上重要」はドイツオリジナルの概念で、内容的に「潰すには巨大すぎる」too big to failの類義語とされる。いったいどのように関係するのだろうか。
2007年のリーマンショックの記憶は生々しい。もし、メガバンクや大手の証券会社や保険会社が倒産すれば、金融システム全体の崩壊を招く。中小企業の連鎖倒産が起こり、失業者が激増し、社会経済システム全般が麻痺してしまうだろう。したがって、金融システムを担う民間企業が巨大であればあるほど、公的資金つまり国民の血税によって救済されなければならない。金融システムの安定上「潰すには巨大すぎる」ゆえに重要なのである。
しかし、ここには「危機」という言葉で隠蔽してはならない資本主義の根本矛盾がある。「詐欺」であることを見抜くには巨大すぎるほどの「不正」がある。新自由主義者は市場原理による競争と淘汰こそが合理的選択であり、政府による干渉は不要だと主張する。政府の機能は出来る限り小さいほうがよい。自由競争に勝ち抜いた企業は、合弁や買収を繰り返して寡占・独占企業へと肥大化する。そこでのモラルは「自己責任論」である。
けれども歴史(文化多様性)や生態系(生物多様性)が教えるように、一人勝ちほど危険なことはない。ところが新自由主義者は、そのリスクを逆手に取る。国家が税金を投入して救済せざるをえないまで巨大化することこそが最も合理的な選択だ、と。「潰すには巨大すぎる」民間企業は倒産を免れるからだ。競争と淘汰のプロセスにおいて負け組となった側は、あらゆる危機の中で身包みを剥がされるが、その間に巨大企業のCEOやマネジャーや投資家は莫大な持ち逃げを許される。金融資本主義のモラルハザードは猖獗を極める。
コロナ危機によって露呈したものは、世界金融の中心ニューヨークで爆発した感染拡大と医療崩壊、すなわち圧倒的な貧富の格差と保険制度の欠陥である。金融資本主義というグローバルな感染症の拡大は、コロナウイルスとともにその感染源を直撃した。いま「システム上重要」なのは、生命の維持に不可欠な医療関係者や、生活に必要なスーパーのレジ打ちなどの「エッセンシャルワーカー」であって、テレワークが可能な投資家やバーチャルエコノミーのエリートたちではない。コロナ危機によって「システム上重要」なものの内実が逆転した。しかし、その所得配分は不公正なままだ。こうした根本矛盾の露呈が、資本主義の終焉を10年単位で前倒にし、新たな社会経済システムの産婆役となることだろう。
これに対してヨーロッパの価値観に共通するものは「社会的」である。「ヨーロッパ統合」という国民国家を超える世界史的実験は、たんに政治統合や市場統合だけでなく、社会的統合を目指す試みでもあった。「社会的経済」(フランス)や「社会的市場経済」(ドイツ)という国是は政権が変わっても維持されてきた。社会的経済が重視する価値は、①資本よりも人間を優先、②訓練と教育による人間発達の重視、③自由意志による結合、④民主的運営、⑤自律とシチズンシップ、である(拙稿「新しい市民社会への仕掛けづくり」、後藤・福原編『市民活動論』有斐閣、2005年、183頁)。
さて、コロナ危機の渦中にあるドイツでは、「誰が、何がシステム上重要なのか?」という問いが百出している。それはもはや金融システムの安定を意味するものではない。いまやシステム上重要なのは、誰が、何が、適切な危機管理によって社会の安定をもたらしているかである。ドイツ連邦共和国大統領シュタインマイヤーは4月11日、テレビ演説で次のように呼びかけた。
「医療現場で命を救う活動に精力的に取り組んでくださっている皆さんへの感謝の念を深くします。私たちの誰もが今、生活全体の激変に見舞われているわけですが、この危機でとりわけ厳しい打撃を受けている人々のつらさを思わずにいられません。病を抱える人々、身寄りのない人々、失業や倒産の心配を抱える人々、収入が激減したフリーランスやアーティストの人々などです。また、バルコニーや庭のない狭い家に住む家庭やひとり親家庭の皆さんの大変さを思います。(…)
私たちがこうして努力を積み上げてきたのは、何も厳格な強制があったからではないはずです。責任感ある市民一人ひとりが支える、生きた民主主義が根づいているからのはずです。一人ひとりが真実と正論の理解に努め、理性的な判断を行い、正しい行動を実行すること、互いに信頼を寄せ合うことのできる民主主義社会、いずれの人の命も尊重され、いずれの人もそれぞれ重要な役割を担っている民主主義です。看護師から首相まで、学術専門家会議から、見える形、見えない形でそれぞれ活躍する社会の様々な支え手まで、皆が役割を担っています。スーパーマーケットのレジを打ち、バスやトラックのハンドルを握り、製パン工房や農場で働き、ごみ収集に従事する人々、そうした人々皆が社会を支えているのです」(https://japan.diplo.de/ja-ja/themen/politik/-/2333154)。
政治家の上から目線はない。シュタインマイヤー大統領は、すべての市民が健気に、相互に信頼を寄せて社会を支え合っていること。誰もがそれぞれの立場から、社会生活の安全と安定のために責任感を持って行動していること。ここにこそ、国家からの強制ではない、生きた民主主義が根付いており、市民社会が機能していることに敬意を表している。つまり誰もが、そしてどのような職業も「システム上重要」なのであり、そのシステムは国家の強制によってではなく、ポトムアップの民主主義として形成され、機能しているのである。
してみると、ドイツの文化関係者が、芸術文化とその議論を通して民主主義を根付かせ、新しい市民社会の形成と発展に大きく寄与してきた点にこそ「文化インフラはシステム上重要である」と主張することの意味と根拠がある。文化政策はけっして「不要不急」のものではない。短期的にも長期的にも「システム上重要」なのである。
もしかりに、芸術文化が緊急時においてシステム上重要あるという社会的合意を得られないとしても、代案として「生きる上で重要だ」Lebensrelevantという言葉が生まれてきている。システムという概念に、なおも金融システムの響きが残っているのであれば、「芸術文化は生きる上で重要である」という表現が定着するほうが好ましいように思われる。
R. v. ヴァイツゼッカー元大統領はドイツ統一直後の1991年、その財政危機の中で次のように語っていた。「文化はたしかに高く付きます。(しかし)文化は、わたしたちがそれを楽しむゆとりがあったり、あるいは取り消したりできるような贅沢品ではありません。そうではなく、わたしたちの内面に本来そなわっている生き抜く力を確実なものにしてくれる精神的な基盤なのです」(https://www.welt.de/print-welt/article509229/Kultur-sichert-Ueberleben.html)。
2.連邦、州、市町村は、文化政策の観点から結束しなければならない。最終的に文化政策的に評価されるべきは、いかに連邦主義と補完性を新たに調整して、文化領域において強靭な構造を打ち立てるか、そして市町村が負担過剰にならないことである。連邦主義と補完性(の関係)が、危機から抜け出す道を分断し、特に市町村にとって過重な負担となってはならない。
ドイツの文化政策の基本3原則は、「文化連邦=分権主義」「州の文化高権」「補完性の原則」である(藤野他編著『地域主権の国 ドイツの文化政策』、19頁以下参照)。ドイツの公的文化歳出の大半は州レヴェルと基礎自治体レヴェルで賄われていおり、2013年の連邦レヴェルでの文化歳出は連邦、州、市町村を合わせた額の13.5%に過ぎない。一般に、連邦政府と州政府との関係は、各州の代表からなる連邦参議院を通して各州政府の意向を連邦政府に反映させる「協調的連邦主義」に基づいて構築される。
しかしながら、文化領域(芸術・文化・メディア・教育)に関しては、「州の文化高権」の原則から州の権限が連邦に優先する。1998年にBKMが創設された際、州の文化高権を侵害しないように、その業務はドイツ全土に関わるもの(首都支援、過去の克服、対外メディアなど)に限定された。しかし、とくに旧東独の新5州に関しては財政面での困窮もあり、2001年末までには文化政策の面でも協調的連邦主義の合意が成立した。ドイツ諸州は、ナチス時代や東ドイツ時代における中央集権的文化政策への不断の反省を前提に、連邦の文化政策との協調と調整を進めてきた。
もとより連邦=分権主義は、各州の多様性が連邦の統一性のなかで保障され展開される、国家制度の原則である。その際に連邦は、各州によっては実行できない広がりをもった中央の課題だけを引き受ける。このメカニズムが「補完性の原則」と呼ばれるものである。この原則は、州と基礎自治体(市町村)の関係にも適用される。
ドイツの行政の仕組みは、連邦、州、市町村の3つの次元に配分されているが、行政事務はできるだけ市民に近いところで行なわれるべきであるとする原則が貫かれている。行政事務の配分は、市町村を基礎として州、そして連邦へと組み立てられている。その際、もし具体的な必要性があり、その効果が総合的に見て市民に有利な場合に限り、より上の段階で処理されるべきものとされる。
文化政策の構造でも「補完性の原則」が尊重されてきた。そのため、文化領域における基礎自治体の負担は文化歳出全体の50%近くに達する。けれども今回のコロナ危機の感染者の割合は、州ごと、自治体ごとに大きな偏差がある。もし補完性の原則に基づいて、基礎自治体の文化インフラを維持し、フリーランスへの支援を行うとすると、財政負担が荷重となる市町村が数多く出てくる。そこで、基礎自治体が負担過剰にならないように、「連邦主義と補完性を新たに調整して、文化領域において強靭な構造を打ち立てる」ことが、文化政策の喫緊の課題となっているのだ。
(づづく)