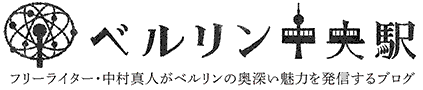ある都市で道が分からないということは、大したことではない。だが、森のなかで道に迷うように都市のなかで道に迷うには、習練を要する。この場合、通りの名が、枯れ枝がポキッと折れるあの音のように、迷い歩く者に語りかけてこなくてはならないし、旧都市部の小路は彼に、山あいの谷筋のようにはっきりと、一日の時の移ろいを映し出してくれるものでなければならない。この技術を私が習得したのは、ずっとのちのことである。
ヴァルター・ベンヤミンの「1900年頃のベルリンの幼年時代」の「ティーアガルテン」の章はこのように始まる(「ベンヤミン・コレクション③記憶への旅」ちくま学芸文庫より引用)。
私がこの本に出会ったのは、2001年の春だったと思う。ベンヤミンに詳しい方から、当時私が住んでいたアパートがベンヤミンが幼年期に住んでいた場所と非常に近い距離にあって、当時のその界隈の様子が描かれていることを教えてもらい、これはぜひ読んでみなければと思ったのだった。私がベルリンで最初に住んだアパートの濃密な思い出とベンヤミンの祖母の家との関連性については、以前書いたことがある。
関連記事:
ベルリン生活は家探しから(3) -100年前のアパート- (2005-11-14)
ベルリン生活は家探しから(4) -歴史との接点-
ベルリン生活は家探しから(5) -ベンヤミンとベルリン-
ベルリン生活は家探しから(6) -「生き残った」アパート-
 高度に詩的で難解な部分もあるこのエッセーだが、冒頭に引用した「ティーアガルテン」の最初の文章は出会った時から好きで、特に「森のなかで道に迷うように都市の中で道に迷う」という感性に惹かれた。その後の文章をいくつか引用してみよう。
高度に詩的で難解な部分もあるこのエッセーだが、冒頭に引用した「ティーアガルテン」の最初の文章は出会った時から好きで、特に「森のなかで道に迷うように都市の中で道に迷う」という感性に惹かれた。その後の文章をいくつか引用してみよう。
そこに至る道はベンドラー橋を渡っていくもので、やわらかに反ったこの橋の昇りが、私にとってはじめて体験する丘の斜面になった。そのたもとからほど遠からぬところに、目指すものがあった。フリードリヒ・ヴィルヘルムの像と、ルイーゼ王妃の像である。円形の台座のうえに聳え立つ彼らは、ひと筋の水の流れがその足許の砂地に描いている魔法の曲線によって呪縛されているかのように、花壇のあいだから姿を覗かせていた。
ベンヤミンがたどったのと全く同じ道を通って、初めてルイーゼ王妃の像の前にたどり着いた時は感動したものだ。また、アパートから徒歩5分の距離にこれだけ静かで心休まる場所があることにも驚いた。

けれども私は、この王侯たちに目をやるよりも、その台座を見ることの方が好きだった。台座に描かれているもののほうが、その意味関連はよく分からなかったにしろ、空間的に身近だったからである。
「ベンヤミン・コレクション③記憶への旅」の充実した注によると、この台座側面のレリーフは対ナポレオン解放戦争時の「婦人の働き」を描いたものだそう。

この迷宮には何かしら重要なものが潜んでいることを、前々から私は像の前広場に感じ取っていた。それはとりとめのない、ごくありふれた広場で、秘密をそっと漏らしているものはそこには何もなかったが、辻馬車や儀装馬車の行き交う大通りからわずかしか離れていないここにこそ、この公園の最も不可思議な部分が眠っているのだ。
ルイーゼ像の前の広場は、初夏になると花々が咲き乱れる非常に美しい庭園なのだが、冬場のこの日はご覧の通り。小さな川の向こうに、フリードリヒ・ヴィルヘルムの像が立っている。
 ティーアガルテンの中をしばらくさまよっていると、マタイ教会(写真奥)のお昼の鐘が白銀の風景の中に溶け込んできた。ベンヤミンのエッセーにも描かれているこの教会の遥かなる響きを聞いていると、どこかしら遠い過去と対話しているような、そんな気分になった。
ティーアガルテンの中をしばらくさまよっていると、マタイ教会(写真奥)のお昼の鐘が白銀の風景の中に溶け込んできた。ベンヤミンのエッセーにも描かれているこの教会の遥かなる響きを聞いていると、どこかしら遠い過去と対話しているような、そんな気分になった。