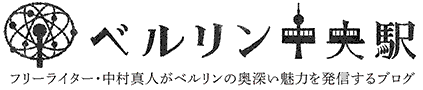久々にブログに向き合う時間ができたので、遅ればせながら2012/13シーズンで印象に残った音楽会やオペラをいくつか振り返ってみたいと思います。
まずオーケストラのコンサートから。
今でも心から楽しかった思い出として残っているのが、昨年11月、イヴァン・フィッシャー指揮ベルリン・フィルの演奏会。ストラヴィンスキーの《カルタ遊び》、プロコフィエフのヴァイオリン協奏曲、ドヴォルザークの交響曲第8番というプログラムでしたが、ドヴォルザークが音楽的に完全無比ともいえる素晴らしさでした。フィッシャーが繰り広げる音楽の表情と響きのパレットの豊かさ、ユーモア、そして終楽章で聴かせたぐつぐつと沸騰するようなダンスの躍動!昨年からコンツェルトハウス管弦楽団の音楽監督を務めるイヴァン・フィッシャーは今、最高に充実のときを迎えているように思います。ベルリン・フィルとの相性もよく、ここ数年は毎シーズンのように呼ばれているのも納得しました。
鮮烈さで印象に刻まれたのが、若手の山田和樹さんが指揮したコンサート。11月末、スイス・ロマンド管弦楽団の主席客演指揮者就任コンサートと5月のベルリン放送響の定期デビュー演奏会を聴きました。5月頭のベルリン放送響のデビュー公演は、チャイコフスキーの交響曲第4番を取り上げたのですが、第2楽章ではじっくり丁寧に歌い上げる一方、フィナーレではマーチ風の主題に絶妙なルバートをかけ、緩急自在の指揮ぶり。聴衆を興奮のるつぼへと導いたのでした。自分と同世代の山田さんが欧州の檜舞台に次々に立つ様子を見ていると、胸がすく思いがします。けれども、ご本人はあくまで自然体。来シーズンはウィーン・デビューも予定されており、若きマエストロ(もちろん彼に限らずですが)をこれからも応援していきたいです。
オーケストラという表現形態がなし得る合奏力のものすごさを見せつけられたのが、マンフレート・ホーネック指揮ベルリン・フィルで聴いたルトスワフスキの管弦楽のための協奏曲(2月)。そして、5月にハンブルクまで出向いて聴いたサロネン指揮フィルハモニア管の《春の祭典》とヴァレーズの《アメリカ》。ソロ協奏曲では、コンツェルトハウス管弦楽団の伴奏で、同オケソロ奏者のピルミン・グレールが吹いたニールセンのフルート協奏曲に興奮しました(5月)。ある作品を自家薬籠のものにするというのはこういうことかと思い知らされた次第。ベルリンのオーケストラのフルート奏者というと、よく脚光を浴びるのはパユさんですが、グレールさんも素晴らしいし、一段と円熟味を増しているベルリン・フィルのブラウさんの音色も他では聴けないもの。ベテランのブラウさんは来シーズンをもってついに引退されるようなので、耳に焼き付けておきたいと思います。
巨匠指揮者では、まず12月にウィーンで聴いたアーノンクール指揮ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスのモーツァルト。楽しみにしていたポストホルン・セレナーデは巨匠の体調不良で指揮者なしの演奏でしたが、楽友協会の黄金のホールに木管楽器の雅な音色がきらめき、冬の寒い日にしみじみと幸福感を味わいました。そして、峻厳なト短調交響曲。このときのライブ録音が今度CDになるようなので楽しみです。
あともう1つは、5月に聴いたアバド指揮ベルリン・フィルでしょうか。今年80歳になるアバドもさすがに大分背中が丸くなり、指揮ぶりにダイナミックさがなくなりつつあるのを感じましたが、特にメンデルスゾーンの《真夏の夜の夢》の格調の高さ、歌わせ方の優美さと響きの透明感は至芸といえるものでした。
2月と3月にオスモ・ヴァンスカ指揮ベルリン・ドイツ響とパーヴォ・ヤルヴィ指揮ベルリン・フィルという、それぞれ好対照の解釈で聴いたシベリウスの交響曲第5番も幸せな体験。合唱作品で感銘を受けたのは、ラトル指揮のブリテンの戦争レクイエム(6月)など。
室内楽で印象に残っているのは、2月のライプツィヒ弦楽四重奏団。ブラームスのピアノ五重奏曲を聴きたくて当日思い立って出かけたら、いかにも好々爺という温和な表情のおじいさん(それもかなりの高齢の)が出てきてびっくりしました。そのピアニスト、メナヘム・プレスラーが、長年ボザール・トリオで活躍した人だと知ったのは恥ずかしながらコンサート後のこと。心からの敬意をもってピアニストに寄り添うカルテットのメンバーと、感動的な瞬間が幾度も生まれたのでした。アンコールのドヴォルザークで聴かせてくれた「軽み」の境地もすごかったです。今年90歳になるプレスラーさん、来シーズンは何とベルリン・フィルにソリストとしてデビュー(!)を果たすそうで、できることならぜひ聴きたいものです。
ピアノでは、昨年10月のツィメルマン、そして3月のフェストターゲで聴いたポリーニが弾くベートーヴェン最後の3つのソナタ。第30番のソナタの終楽章、いくつもの変奏を経て主題が戻ってくるときのえもいえぬ感動は、巡礼の旅の最後でそれまで見たこともない美しい夕暮れに出合ったような、そんな光景を思い起こさせるものでした。
オペラでは、コーミッシェ・オーパーで観たヘンデルの《セルセ》(ヘアハイム演出)や《魔笛》などがよかった。後者はバリエ・コスキー演出による、無声映画とアニメーションの要素を組み合わせた奇妙に斬新な舞台で、ベルリンでも異例のヒットを続けています。ラトルが指揮した国立歌劇場の「ばらの騎士」では、レシュマン、コジェナー、プロハスカらが織りなす歌によるアンサンブルの美に酔いました。そして忘れられないのが、1月に観た細川俊夫作曲のオペラ「松風」。サシャ・ヴァルツの振付、塩田千春による細い糸を無数に絡ませた舞台美術、そして毛筆を思わせる細川さんの躍動的かつ幽玄な音楽。日独の芸術家による共同制作としては、近年稀に見る成果と言えるのではないでしょうか。それほど長い時間の作品ではないのに、観終わってから確かに心の中が浄化されたような、そんな芸術体験でした。
(ここからは余談ですが)アマチュアオーケストラでの自分の演奏体験を振り返ると、一番強烈だったのが2月に演奏したショスタコーヴィチの交響曲第11番。夏学期にはがらっと変わってビゼー、サンサーンス、ラヴェル、デュカスのフランス音楽のプログラムを演奏しました。ピッコロのパートは難しかったけれども、その響きの魔術に何度も陶然としたのがラヴェルの《マ・メール・ロワ》。次の冬学期ではマーラーの《復活》を演奏することになり、マーラーの交響曲を初めて吹けるのかと思うと、今から楽しみです。
この1週間はバイロイト音楽祭で新演出の「リング」に接する機会に恵まれました。こちらもいろいろな意味で忘れがたい体験だったので、落ち着いたらじっくり振り返りたいと思っています。