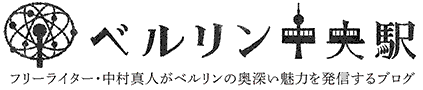この3月半ば、ベルリン日独センターで、東日本大震災に関連した2本の長編ドキュメンタリー映画が上映されました。
大震災から7年が経過し、日本でも記憶の風化が叫ばれるようになっています。「ドイツでは原発や放射能に関する問題に対して敏感だが、津波で被害を受けた街や集落での、当事者側の視点に立った情報がほとんど入ってこない」(清田とき子副事務総長)。このような現況を鑑みて、同センターは今回の上映会に我妻和樹監督による『波伝谷に生きる人びと』とその続編に当たる『願いと揺らぎ』を選んだといいます。
波伝谷は、宮城県の南三陸町にある小さな漁村。学生時代に波伝谷での民俗調査に参加し、強い印象を受けたという同県白石市出身の我妻監督は、2008年から個人で波伝谷のドキュメンタリー映画を撮り始めます。『波伝谷に生きる人びと』には、この地に古くから伝わる「お獅子さま」という厄払いの行事を軸に、漁業を中心とする人びとの営み、契約講という独特の自治組織の様子などが緩やかな時の流れの中で描かれています。
しかし、2011年の大震災で波伝谷は壊滅的な被害を受け、地域のコミュニティも断ち切られました。『願いと揺らぎ』では、震災1年後にある若者から上がった「お獅子さま」の復活の過程が、さまざまな紆余曲折を経て記録されています。
私が興味深かったのは、困難を抱えた波伝谷の人びとの揺らぎと共に、部外者としてカメラを回し続ける我妻監督自身の心の葛藤が映像に読み取れることでした。小さなコミュニティの人間関係に配慮しながらも、確かな意志をもって、彼らの心の内奥により深く入っていくのです。撮影者の情熱は、終幕に近いあるシーンで結実します。人びとの考えの相違や摩擦から「お獅子さま」の復活に向けた方向性が変わっていったことで、いつしかそこから距離を置き、心にわだかまりを抱えていた若者が、5年近い月日を経て当時の思いを語る場面。時の重みの中で語られる独白は、「矛盾を抱えながらも、人は共に生きていく」というメッセージへとつながっていきます。
「作品のストーリーが決して分かりやすいものではないことと、海外から見た日本の震災のイメージが一面的との話を聞いていたこともあって、作品がどのように受け止められるか不安でした。しかし皆さん、遠くに住む自分の親戚の日常や苦悩を見るように身近なものとして捉えてくださって嬉しかったです。その意味では、ドイツの方々にとっての震災のイメージを少し広げることができたのではないかと思います」(我妻監督)
この映画のポスターには「被災地の人びとが生きた証の、ほんの一部の記録」と書かれています。震災の節目に際して、その土地に生きる具体的な人たちに思いを寄せることができた夜でした。
(ドイツニュースダイジェスト 4月20日)