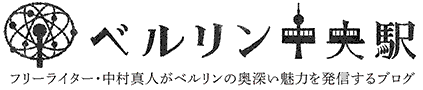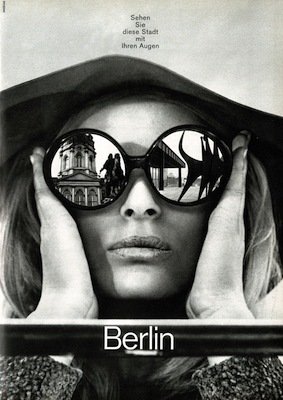Rainer Fetting: Potsdamer Platz, 1993/95 © Rainer Fetting | Stadtmuseum Berlin | Reproduktion: Oliver Ziebe
ミッテ地区のニコライ教会からほど近いエフライム宮殿で、「大都市の美」という展覧会が開催されています。これは19世紀前半から現代まで、都市ベルリンをモチーフに描かれた絵画を一堂に集めた企画展です。生粋のベルリンっ子の知人から「この街に住んでいると一層楽しめるわよ」とすすめられていたのを思い出し、足を運んでみました。
入り口から中に入ると、1冊の古い本がショーケースの中に収められていました。この展覧会のタイトルになっている「Die Schönheit der großen Stadt」という1908年の本。筆者の哲学者・建築家のアウグスト・エンデルは、ハッケシェ・ヘーフェの中庭をデザインしたことで知られます。
最初の部屋で飛び込んできたのは、ライナー・フェティングが1990年代初頭に描いた「Potsdamer Platz」。緑の向こうにベルリン・フィルハーモニーの黄色い建物が浮かび、その右側には建設中のポツダム広場のクレーンがいくつもそびえています。東西を分け隔てていたベルリンの壁がなくなってまだ数年という当時、空の開放感が一際迫ってくる作品でした。別の部屋で出会ったローラント・ニコラウス作の「動物のための広場」(1989)では、同じポツダム広場を描きながらも、主役は壁の緩衝地帯に生息する動物たち。壁が人間だけでなく動物の生活をも翻弄したことが、ある種のユーモアをもって伝わってきます。
この展覧会は作品を時代別に並べるのではなく、「屋根の上で」「大都市の夜」「工事現場ベルリン」「引き裂かれた都市」「都市のきわで」など、テーマ別にさまざまな時代の作品を並列させているのが特徴。写真と違って絵具の鮮やかさが残る絵画には時間の感覚を麻痺させる効果があり、最近の作品を観た後、アルトゥール・アーロン・ゼガール作の「ベルリンの街角の風景」(1912)の鮮やかな色使いにはっとしたことも。
戦争で多くが失われたとはいえ、それでも過去との確固たる連続性が残っているのもまたベルリンという都市です。その絵に描かれている場所を探したり、現在の風景と重ね合わせたりするのは、この展覧会の大きな楽しみといえます。ノレンドルフ広場を描いたものだけでも、ベックマン(1911)、キルヒナー(1912)、ユリィ(1925)など何人もの画家の作品に出会えたのはこのような企画ならでは。自宅のバルコニーからの夕暮れ時の風景を描いたエルンスト・フリッチュ作の「Sender Witzleben am Abend」は、ナチスが政権を取った1933年作という歴史的事実を重ね合わせることで、日常の風景が別の意味をもってきます。
ベルリンは流麗な街並みの美を誇る都市ではないかもしれませんが、画家個人の視点から、この街ならではの美が浮かび上がってくる展覧会になっています。開催は8月26日まで。
「大都市の美」: www.stadtmuseum.de/schoenheit