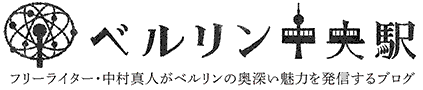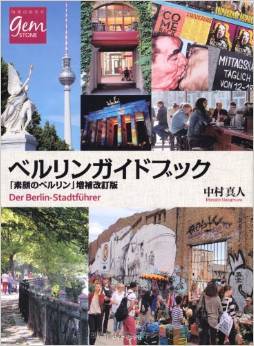とびとびの連載になってしまったが、ザクセンハウゼン強制収容所の規模の一端をいくらかお伝えできただろうか。午前中にベルリンを出発しても、強制収容所の奥にあるクレマトリウムまで見学して、再び収容所の門に戻る頃には、大体もう夕方になっている。
 最後に訪れるのは、独房棟(Zellenbau)と小収容棟(Kleines Lager)と呼ばれるバラック跡だ。冬期の閉館時間は16時半。薄暗く人気の少ないバラックの中に入るのは、正直ちょっとこわい。
最後に訪れるのは、独房棟(Zellenbau)と小収容棟(Kleines Lager)と呼ばれるバラック跡だ。冬期の閉館時間は16時半。薄暗く人気の少ないバラックの中に入るのは、正直ちょっとこわい。
 こちらがゲシュタポと収容所の監獄だった独房棟の内部。壁によって周囲からは隔離された中に、かつて80の独房があった。反ナチのマルティン・ニーメラー牧師(1892-1984)など、特に影響力のある収容者もこの中に拘留していたという。
こちらがゲシュタポと収容所の監獄だった独房棟の内部。壁によって周囲からは隔離された中に、かつて80の独房があった。反ナチのマルティン・ニーメラー牧師(1892-1984)など、特に影響力のある収容者もこの中に拘留していたという。
 ここを抜けると、処刑台が当時のままの状態で残されている。壁によって外からは見えないこの場所で、残酷な虐待や殺害が密かに行われたのだった。
ここを抜けると、処刑台が当時のままの状態で残されている。壁によって外からは見えないこの場所で、残酷な虐待や殺害が密かに行われたのだった。
 そして小収容棟に属していたバラック38と39。1938年11月から42年10月までの間、ユダヤ人の収容者はすべてここに詰め込まれていた。
そして小収容棟に属していたバラック38と39。1938年11月から42年10月までの間、ユダヤ人の収容者はすべてここに詰め込まれていた。
 ドイツ統一後の1992年、両方のバラックは反ユダヤ主義者によって放火されたそうで、特にバラック38の方には天井に焼け跡が生々しく残っている。そのためか、囚人のベッドがぎっしり置かれた部屋はガラス越しにしか見ることができない。
ドイツ統一後の1992年、両方のバラックは反ユダヤ主義者によって放火されたそうで、特にバラック38の方には天井に焼け跡が生々しく残っている。そのためか、囚人のベッドがぎっしり置かれた部屋はガラス越しにしか見ることができない。
 私が初めてここを訪れた2007年冬、小収容棟からA塔に戻るときの夕暮れの風景と凍てつくような寒さを思い出す。同じ年、アウシュヴィッツを訪れた際も、どういうわけか、とても美しい夕暮れを見たのだ。ヴィクトール・フランクルの『夜と霧』(みすず書房)の中で、彼がアウシュヴィッツから別の収容所に貨物列車で輸送されたとき、隙間から見えたアルプスの山々の神々しい美しさに感動し、これだけ人間性を蹂躙されてなお、美に感動する精神が残っていたことに自分自身驚くという印象的な箇所がある。もしも自分が同じ立場に置かれたら、あの夕焼けを見て、何かを感じられるのだろうか・・・。
私が初めてここを訪れた2007年冬、小収容棟からA塔に戻るときの夕暮れの風景と凍てつくような寒さを思い出す。同じ年、アウシュヴィッツを訪れた際も、どういうわけか、とても美しい夕暮れを見たのだ。ヴィクトール・フランクルの『夜と霧』(みすず書房)の中で、彼がアウシュヴィッツから別の収容所に貨物列車で輸送されたとき、隙間から見えたアルプスの山々の神々しい美しさに感動し、これだけ人間性を蹂躙されてなお、美に感動する精神が残っていたことに自分自身驚くという印象的な箇所がある。もしも自分が同じ立場に置かれたら、あの夕焼けを見て、何かを感じられるのだろうか・・・。
5回に分けてザクセンハウゼン強制収容所の主要な場所をご紹介してきたが、医療殺人や人体実験なども行われた医療棟のバラック(Krankenrevierbaracken)や地下に死体安置場を備えた病理学棟(Pathologie mit Leichenkeller)までは書き切れなかった(もっとも、それについての展示を見るのも書くのも、相当なエネルギーが要りそうだ・・・)。収容所の一番奥にあるソ連時代の特設収容所跡には、まだ私も行ったことがない。とにかく、丸1日ですべてを見られる規模ではない。
ベルリンの周辺でこれほど気が滅入る場所もないけれど、それでも何かを感じるべき場として、一度は訪問されることをお勧めしたい。やはりアウシュヴィッツの生還者であるイタリア人のプリーモ・レーヴィが、『アウシュヴィッツは終わらない』(朝日選書)の中で記しているように。
ナチの憎悪には合理性が欠けている。それは私たちの心にはない憎悪だ。人間を超えたものだ。ファシズムという有害な幹から生まれた有毒な果実なのだが、ファシズムの枠の外に出た、ファシズムを超えたものだ。だから私たちには理解できない。だがどこから生まれたか知り、監視の目を光らすことはできる。またそうすべきである。理解は不可能でも、知ることは必要だ。なぜなら一度起きたことはもう一度起こりうるからだ。良心が再度誘惑を受けて、曇らされることがありうるからだ。私たちの良心でさえも。
最後にもう一つ、レーヴィの体験記の中から、彼が後年若い読者に向けて書いた一節を引用したい。これはいまの時代に当てはめても考えることのできる箴言ではないだろうか。
彼ら(ナチスの信者たち)は何の変哲も無い普通の人だった。怪物もいないわけではなかったが、危険になるほど多くはなかった。普通の人間のほうがずっと危険だった。何も言わずに、すぐに信じて従う職員たち、たとえば、アイヒマン、アウシュヴィッツの所長だったヘス、トレブリンカの所長だったシュタングル、20年後にアルジェリアで虐殺を行ったフランスの軍人たち、30年後にヴェトナムで虐殺を行ったアメリカの軍人たち、のような人々だ。
だから、理性以外の手段を用いて信じさせようとするものに、カリスマ的な頭領に、不信の目をむける必要がある。他人に自分の判断や意思を委ねるのは、慎重になすべきである。予言者を本物か偽物か見分けるのは難しいから、予言者はみな疑ってかかったほうがいい。啓示された真実は、たとえその単純さと輝かしさが心を高揚させ、その上、ただでもらえるから便利であろうとも、捨ててしまうほうがいい。もっと熱狂を呼び起こさない、地味な、別の真実で満足するほうがいい。近道をしようなどとは考えずに、研究と、討論と、理性的な議論を重ねることで、少しずつ、苦労して獲得されるような真実、確認でき、証明できるような真実で満足すべきなのだ。
『アウシュヴィッツは終わらない あるイタリア人生存者の考察』(プリーモ・レーヴィ著。朝日選書)のP245より