11月16日、ベルリン日独センターの「対話サロン」にて、異色の対談が実現しました。オーケストラ・合唱団のバッハ・コレギウム・ジャパンの音楽監督で、この6月に日本人として初めてライプツィヒ市より「バッハ・メダル」を受賞した鈴木雅明氏と、革新的なダンス作品を世に送り出し、近年はオペラの分野にも進出している振付家のサシャ・ヴァルツ氏。実はこの日初対面という2人の対談には多くのファンが詰め掛け、会場はほぼ満員となりました。
同センターの河内彰子文化部長が司会を務めた対談では、まず2人の芸術家が古楽、舞踊に目覚めたきっかけについて語られました。最先端のアートを学びたくて、2人が留学先として選んだのは、偶然にも同じアムステルダムだったとか。
数年前、初めて古楽アンサンブルと共演し、「そこに開かれた即興の要素」を感じたというヴァルツ氏に対し、鈴木氏はこう反応します。「ヴァルツさんの作品で、たくさんのダンサーの体がまとわり付くように反応しているのを見て、対位法的なラインのようなものを感じました。作曲家個人の思いに縛られている19世紀以降のロマン派音楽と違い、古楽では音楽そのものが自由を求めていて、自然な音の形を表現することがとても大切。それを舞踊という目に見える形で表現されているように感じたんです」。
古楽とコンテンポラリーダンス。相反するようでいて、実は意外と近いところにあるようです。話題は、芸術における身体コミュニケーションへと移ります。
「演奏において絶対的に重要なのは呼吸。呼吸を通して、体の動きが自然なものとなるからです。日本語で言う『気』は、呼吸と一体なのです」(鈴木氏)。「演じる側と聴衆の間に、私もそのようなエネルギーの流れを感じることがあります」(ヴァルツ氏)。「オーケストラを指揮している最中、何の合図もしていないのに、あるメンバーの方を見て、その人とふと目が合う瞬間がある。このような気の交流は最高に楽しい」(鈴木氏)
最後の質疑応答では、鈴木氏が長年取り組んできたバッハの話が印象に残りました。「僕は信仰心からバッハの音楽に入ったのではなく、彼の音楽に捕らえられ、やりたいことを一生懸命やってきただけ。18世紀半ばまで、音楽というのは芸術ではなく、ある目的のために機能すべき職人芸だったんです。だから、バッハの音楽は今日においても芸術作品として鑑賞するだけでなく、慰められたり、励まされたり日常的に役に立てられるもの。いわば、毎日食べて栄養になるお米と同じ。決して高級レストランの食事というわけではありません(笑)」。
対談中、「もし(ヴァルツ氏のレパートリー作品である)『ディドとエネアス』を日本で上演することがあったら、僕らが伴奏しますよ」という鈴木氏の突然の提案に対し、ヴァルツ氏が「それは良いアイデアですね!」と返す場面がありました。2人の芸術家の自由な精神が言葉の端々に感じられた対談。近い将来、夢の共演は本当に実現するのかもしれません。
(ドイツニュースダイジェスト 12月21日)
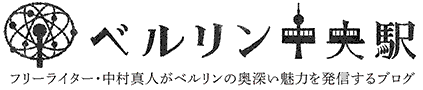












SECRET: 0
PASS:
こんにちは。サシャ・ヴァルツに興味が湧いて2006年のインタヴュー記事を読ませていただきました。とても知的で前衛的なダンスを見せてくれるようですね。オランダのイリ・キリアン率いるネザーランドダンスシアターは、来日すると観に行きます。(めったに来日しないのですが)そこに所属していた日本人ダンサーもいて、その人たちの公演は時々観ています。ヴァルツの振付した作品をベルリンでぜひ見て観たいです。
SECRET: 0
PASS:
tsu-buさん
2006年に訳したサシャ・ヴァルツのインタビュー記事を読んでくださったんですね。あの頃は時間だけはあったので、ブログでもいろいろ書いたなあと思います(笑)。サシャ・ヴァルツはあの後も定期的に新作を発表していますが、私は4月に彼女の初期のTravelogueというダンスを観る機会があり、それは最高に楽しいものでした。ベルリンに長く住む人の中には、「サシャは昔の方が面白かった」なんて言う方もいますが、私は彼女のこれからの活動にも注目したいと思っています。