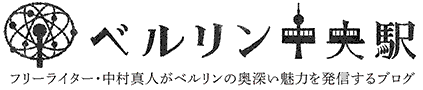筆者は2003年からバイロイト音楽祭のチケットを毎年申し込み続けてきた。「外れても、とにかく送り続けることよ。それが大事」と知人のワグネリアンの方に諭され続けて早10年、今年ついに「当選」の通知が届いた。奇しくもワーグナーの生誕200周年というメモリアルイヤー。その中で一番の注目を集めた「ニーベルングの指環」新演出を体験することができた。
(ドイツニュースダイジェスト 9月20日)
「ニーベルングの指環」は4夜に分けて上演される、音楽史上稀に見る大作だ。記念すべき年の新演出を任されたのは、ベルリンのフォルクスビューネで長年芸術監督を務めるフランク・カストルフ。旧東独出身のカストルフは、指環をめぐる物語を米国やロシアといった超大国による「石油」をめぐる争いに置き換えた。「ラインの黄金」は米国の「ルート66」のガソリンスタンドとモーテル、「ワルキューレ」ではアゼルバイジャンの油田が舞台という具合に。「ジークフリート」の後半では、ベルリンのアレクサンダー広場が登場する。殺伐とした情景の中で、ジークフリートがカーニバルのパレードから飛び出したかのような派手な衣装をまとった森の小鳥と出会うシーンは、とても印象的だった。
ところがその後、「事件」が起こる。ようやく出会ったジークフリートとヒロインのブリュンヒルデが愛の歓喜を歌い上げるのだが、どうもお互いにあまり関心を持っていない様子。しかも、そこになぜか2 匹のワニが現れて、森の小鳥を食べてしまう。何時間も堅い椅子に座って聴き続けてきたワグネリアンにとって、普通ならば一番のカタルシスを味わうシーンだけに、最後の音が鳴り止むと、かつて体験したことのないほどのブーイングが劇場内に飛び交った。
オペラの休憩中、ワーグナー研究家の北川千香子さんにお会いした。北川さんは、2005 年から会場係の仕事をしながらこの音楽祭と関わり続けている。お話の中で印象に残ったのは、バイロイトに来てすぐの頃に出会ったというクリストフ・シュリンゲンジーフ演出の「パルジファル」のこと。「とても『変な』演出の舞台で、評判も悪かったんです。でも、即興性が豊かで、観る度に違うことが起こる。一体、演出家は何を意図して、あの舞台を作ろうとしたのか考えていったんです」。
北川さんはそれを機に「パルジファル」をテーマとする博士論文を書き上げた。「実験工房」の色が濃いバイロイトにおいて、ブーイングが起こるのはさほど珍しいことではないが、彼女の場合、その強烈な印象が立ち止まって考えるきっかけになったのだ。
最終日「神々の黄昏」の最後では、ニューヨークの証券取引所が目の前に現れた。結局、石油との関連性は不明確なままだったが、カストルフが込めようとしたであろう社会主義国家の理想と挫折、忘却。そして大国間の利権争い。それは、冷戦後の今も根本においてそう変わっていないのではないかと思わせる妙なリアリティーを残し、幕は閉じられた。
ところで今回、知人のワグネリアンのお孫さん、アダム君がバイロイト音楽祭に「デビュー」を果たした。5歳のアダム君は幕間に、好奇心たっぷりに周囲に質問を投げ掛け、約6時間の「ジークフリート」を最後まで見通した。舞台だけでなく、聴衆側にも新しい風あり。ワグネリアンはこうして次の世代へと受け継がれてゆく。
ワーグナーの生誕250年の頃には、アダム君は55歳。私は果たして生きているのか微妙な年代だ。その頃、世界はどうなっていて、指環は何に置き換えられているだろう。緑豊かなこぢんまりとしたバイロイトの町で、世の行く末に思いを馳せる。世界の生成と崩壊を描いたワーグナーの芸術には、そんな壮大な思いに至らせる何かがある。