2007年に私が初めてザクセンハウゼン強制収容所跡を訪れたとき、正三角形の頂点に近い位置まで歩いたのだが、そこで引き返してしまった。それだけに、その数年後、壁の向こうに「隠れて」いたものを目にした驚きは大きかった。
 この場所に立ってみれば、これが銃殺用に作られた塹壕だということがすぐにわかるだろう。博物館のパンフレットには、「抵抗運動の闘士、兵役拒否者もしくはナチ特別裁判所で有罪判決を受けた者が処刑された」とある。奥まで寄って見上げてみたら、処刑のときに使われたであろう釣り鉤がまだ生々しく架かっていた。
この場所に立ってみれば、これが銃殺用に作られた塹壕だということがすぐにわかるだろう。博物館のパンフレットには、「抵抗運動の闘士、兵役拒否者もしくはナチ特別裁判所で有罪判決を受けた者が処刑された」とある。奥まで寄って見上げてみたら、処刑のときに使われたであろう釣り鉤がまだ生々しく架かっていた。
 横の壁には、ヨーロッパの各国語で書かれた記念碑が掛けられていた。ドイツから見た「外国人」の多くもここで殺されたのだった。
横の壁には、ヨーロッパの各国語で書かれた記念碑が掛けられていた。ドイツから見た「外国人」の多くもここで殺されたのだった。
この塹壕の隣には、目立たないが墓地の跡がある。火葬場で焼かれた犠牲者の灰が、親衛隊によってここでまかれたという。
そしてもう一つ、私がわかっていることがある。あの当時、途方もない侮蔑と憎しみの中で殺され、拷問や空腹の中で死に至り、ガス室で殺され、絞首刑で殺戮された人々のことを国籍問わず心に刻むことなしに、将来のヨーロッパは存在し得ない。
Andrzej Szczypiorski, 1995
かつてザクセンハウゼンの捕虜だったAndrzej Szczypiorskiという人の言葉が刻まれた入り口から中に入ると、そこは火葬場跡。ここは「Z部」と呼ばれ、現在ザクセンハウゼン強制収容所の犠牲者の中央追悼所になっている。ザクセンハウゼンに来て、毎回いくらかの希望を感じることができるのは、いつ訪れても若い人々のグループに出会うことだ。

 1942年、ここにガス室と4つの焼却場からなるクレマトリウムが造られた。『戦時下のベルリン』(ロジャー・ムーアハウス著。白水社)という本によると、ガス室はシャワー室に見せかけられ、もはや働けなくなった囚人を処刑するために使われたという。この建物は1952年に爆破されたので、現在残るのは土台部分だけである。私はてっきりナチスが証拠隠滅のために爆破したのかと思っていたが、年号を見るとそうではないようだ。
1942年、ここにガス室と4つの焼却場からなるクレマトリウムが造られた。『戦時下のベルリン』(ロジャー・ムーアハウス著。白水社)という本によると、ガス室はシャワー室に見せかけられ、もはや働けなくなった囚人を処刑するために使われたという。この建物は1952年に爆破されたので、現在残るのは土台部分だけである。私はてっきりナチスが証拠隠滅のために爆破したのかと思っていたが、年号を見るとそうではないようだ。
 強制収容所跡を訪れて何を考え学ぶべきか、戦後30年の年に生まれた私はなかなか実感を持って語ることができない。それゆえ、最近読んで感銘を受けたアウシュヴィッツの生存者、プリーモ・レーヴィの著作からの一節を最後に引用したい。1947年に書かれた文章だが、ラーゲル(強制収容所)は「いま」の問題であり続けているのだと考えざるを得ない。
強制収容所跡を訪れて何を考え学ぶべきか、戦後30年の年に生まれた私はなかなか実感を持って語ることができない。それゆえ、最近読んで感銘を受けたアウシュヴィッツの生存者、プリーモ・レーヴィの著作からの一節を最後に引用したい。1947年に書かれた文章だが、ラーゲル(強制収容所)は「いま」の問題であり続けているのだと考えざるを得ない。
個人にせよ、集団にせよ、多くの人が、多少なりとも意識的に、「外国人はすべて敵だ」と思いこんでしまう場合がある。この種の思いこみは、大体心の底に潜在的な伝染病としてひそんでいる。もちろんこれは理性的な考えではないから、突発的な行動にしか現われない。だがいったんこの思いこみが姿を現わし、いままで陰に隠れていた独断が三段論法の大前提になり、外国人はすべて殺されなければならないという結論が導き出されると、その行きつく先にはラーゲルが姿を現わす。つまりこのラーゲルとは、ある世界観の論理的発展の帰結なのだ。だからその世界観が生き残る限り、帰結としてのラーゲルは、私たちをおびやかし続ける。であるから、抹殺収容所の歴史は、危険を知らせる不吉な警告として理解されるべきなのだ。
『アウシュヴィッツは終わらない あるイタリア人生存者の考察』(プリーモ・レーヴィ著。朝日選書)の序文より
(つづく)
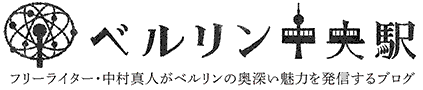











SECRET: 0
PASS:
マサトさんにガイドをして頂いている気分でこのシリーズを大変興味深く拝見しています。向こう側にあったものに、衝撃を受けました。こうやって残されているとただ記念碑だけを見るより当時の空気まで伝わってきそうですね、重みを感じます。続きも待っています。
SECRET: 0
PASS:
ゴン太さん
コメントありがとうございます。アウシュヴィッツを訪れたときもそうでしたが、こうして人目につきにくい場所にこそ、残酷な「装置」が隠されていて、驚愕したことが何度かあります。あと2回ほど書くつもりなので、どうぞお付き合いくださいね。