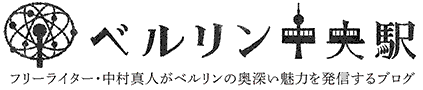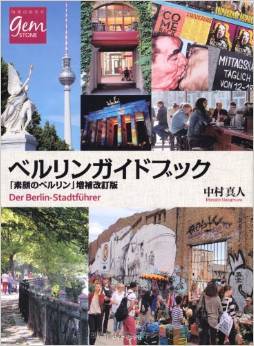発売から大分時間が経ってしまいましたが、最近寄稿する機会のあった季刊誌「考える人」の夏号をここでご紹介したいと思います。昨年秋、この雑誌にまつわる個人的な回想録(こちら)を書いたことがあり、いつかこういう雑誌に寄稿できたらと漠然と願っていましたが、まさかこんなに早く実現するとは思いませんでした。春に執筆依頼をいただいたときは飛び上がりたくなるほど嬉しかったです。
発売から大分時間が経ってしまいましたが、最近寄稿する機会のあった季刊誌「考える人」の夏号をここでご紹介したいと思います。昨年秋、この雑誌にまつわる個人的な回想録(こちら)を書いたことがあり、いつかこういう雑誌に寄稿できたらと漠然と願っていましたが、まさかこんなに早く実現するとは思いませんでした。春に執筆依頼をいただいたときは飛び上がりたくなるほど嬉しかったです。
夏号の特集は「文庫」。今年新潮文庫が100周年を迎えることからこのテーマが選ばれたそうで、日本の文庫本のみならず、古今東西の小型本の魅力がたっぷりと語られています。今回私が編集部からいただいた依頼内容は、「日本の文庫に大きな影響を与えたドイツのレクラム文庫。それも、東西分断の時代のレクラムについて書いてほしい」というもの。いかにも「考える人」らしい、渋いテーマだなと思いました。実は、もともとライプツィヒに本社を構えていたレクラム社は、東西ドイツの分断後、非常にドラマチックな過程を経て、会社自体も東西に引き裂かれているのです。最初漠然と思ったのは、東西それぞれのレクラムの視点から描けたら、面白い記事になるのではないかということでした。まず、シュトゥットガルトの近くにある現在のレクラム本社にコンタクトを取ってみたのですが、正直あまりいい反応が得られず、どうしようかと思っていたところ、ライプツィヒ大学に東独時代のレクラム文庫の研究をしているグループがあることを知りました。早速連絡を取ってみたところ、同大書籍学のイングリッド・ゾンターク先生が快く取材に応じてくださることになりました。
 4月にライプツィヒを訪ねて伺ったゾンターク先生のお話は予想以上に面白く、5月にも再訪することになりました。正直なところ、私はそれまで東独のレクラム文庫に対して、ごく大雑把なイメージしか持っていませんでした。名門のレクラム社とはいえ、東ドイツという社会主義国家の中では、体制の意向に添う形の書物しか出せなかったのではないかと・・・。確かに一面ではそうだったのですが、レクラムの社長と、Lektorと呼ばれる企画顧問からなるチームの人々が、限られた条件の中でいかに知恵を絞り、面白い本、そして人々に思考を促す本を出そうと努力していたか、その葛藤を生々しく聞き知ることとなりました。
4月にライプツィヒを訪ねて伺ったゾンターク先生のお話は予想以上に面白く、5月にも再訪することになりました。正直なところ、私はそれまで東独のレクラム文庫に対して、ごく大雑把なイメージしか持っていませんでした。名門のレクラム社とはいえ、東ドイツという社会主義国家の中では、体制の意向に添う形の書物しか出せなかったのではないかと・・・。確かに一面ではそうだったのですが、レクラムの社長と、Lektorと呼ばれる企画顧問からなるチームの人々が、限られた条件の中でいかに知恵を絞り、面白い本、そして人々に思考を促す本を出そうと努力していたか、その葛藤を生々しく聞き知ることとなりました。
数日前、今回のレクラムの記事を読んだ、知人の新聞記者の方が、こんな感想を寄せてくださいました。
一企業としてのレクラムが、これほど東独の精神文化を背負っていた存在だったとは驚きでした。私は去年、メルケル首相の小学校時代の同級生(ドレスデンの外科医)に会いに行ったのですが、取材の中で、すでに幼少期から秀才だったメルケルは、10歳くらいでレクラムを読んでいた、という話をこの同級生から聞いたのを思い出しました。今思えば、それこそがこの東独レクラムだったのですね。レクラムは、今各界で活躍している多くの東独出身者の知性・感性を、確かに育てていたのでしょうね。
今回の原稿用紙10枚という文字数は、普段私が書く原稿に比べると多めだったのですが、実際書く段階になると、いかに集めた素材を削るかで苦心することになりました。
いまは亡き東ドイツという国の知られざる本をめぐるお話を、お読みいただけたらうれしく思います。もちろん、「考える人」夏号は、じっくり読んだら一夏かかりそうなほど、他にも読み応えのある記事が満載です。