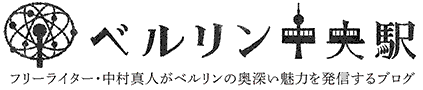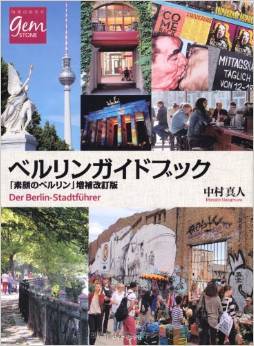小学生の頃からクラシック音楽が大好きだった。別に「クラシック音楽」だからというので近づいていったのではない。小学2年生のとき、たまたま転校先の学校の掃除の時間にモーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」が流れていて、毎日聴いているうちに好きになったのである。そういうわけで、その音楽を生み出す母体である「オーケストラ」というものに対しても自然と興味を抱くようになった。
生のオーケストラを聴いて、初めて心の底から揺り動かされた。そんな衝撃的ともいえる原体験が私にはある。それはベルリン・フィルでもウィーン・フィルでもなく(さすがに当時生で聴く機会などなかった)、かといって地元のプロのオケでもなく、日本の10代の少年少女が演奏するオーケストラだった。
1988年の1月末だったと思う。小学6年生だった当時、私はリコーダーの音色が好きで、リコーダーアンサンブルのクラブに入っていた。山本典子先生の指導のもと、横須賀市立森崎小学校の音楽クラブはTBSこども音楽コンクールの東日本大会に出場した。会場は東京の郵便貯金会館だったと思う。東京での大舞台ということで緊張もあったのか、私たちのクラブは力を十分に出し切れず、やや不甲斐ない気持ちのまま残りの学校の演奏を聴いていた。今でもよく覚えているが、最後の2つの小学校はオーケストラ演奏だった。確か2つとも千葉県の公立の学校で、そしてなぜか二校ともドヴォルザークの新世界交響曲の第4楽章を演奏した。そして、これがすごかったのだ。
音楽自体のかっこよさはもちろんのこと、その音が放射するエネルギーと輝かしさに圧倒された。何より目の前で音を奏でているフルオーケストラのメンバーが、自分と年の変わらない小学生であるという事実・・・。あれこそが、「自分もいつかあの中に入って音楽をしてみたい!」と真剣に思った最初の瞬間ではなかったかと思う(もちろん、金賞に輝いたのはこの2つのどちらかのオーケストラだった)。幸い私は、アマチュア音楽家にしてはこれまでかなり恵まれたオーケストラ環境で音を奏でることができた方だと思う。いろいろな意味で、心が震えるような体験をしたことも一度や二度ではないし、仲間とのアンサンブルの難しさや苦労も含めて、オーケストラという世界で学んできたことは数限りない。
前置きが長くなってしまった。最近発売になった新潮社の季刊誌「考える人」秋号の特集は「オーケストラをつくろう」。前から愛読していた雑誌がこんなテーマの特集を組むとは、やはりちょっと興奮させられた。オーケストラ特集といっても、「ベルリン・フィルの演奏がいかに素晴らしいか」とか、「あの指揮者のあの曲の何年盤の録音がどうのこうの」といった音楽専門誌の視点ではなく、オーケストラそのものが持つ可能性と夢について存分に語っているのが面白い。紹介されるのも、プロの第一線で活躍する音楽家もいれば、50歳以上でないと入れない「老人オケ」、小学校の PTAを母体にした親子アンサンブルもある。特集の核になっているのが、ベネズエラから始まり世界に旋風を巻き起こしたエル・システマだ。いわば、「エリートだけではないオーケストラ」がテーマともいえる。
曲がりなりにもにもオーケストラに長年関わってきたからゆえに、(時にいくばくかの自省の念とともに・笑)共感を持って感じられる言葉に数多く出会った。例えば・・・
〈私もクラシックのアマチュアオーケストラに入っているので身にしみて分かるが、この種の団体を運営するのは本当に大変だ。練習場の確保、経理、連絡事務、楽譜管理。演奏会をやればホールとの交渉、受付や案内係の手配といった雑用が山のようにある。ところが音を出す以外の仕事はみんなやりたがらない。一方で選曲や練習方法の話になるとてんでに勝手を言う。そのうちに人間関係がもつれてくる。そのあたりが小説にする時の妙でもあったけれど、現実にもゴタゴタ続きの団体は枚挙に暇がない〉(荒木源「実録『オケ老人!』」より)
〈なぜそこまでして、オケに打ち込めるんだろう?
「それはもう・・・・・・アンサンブルで音が合ったときの喜びといったら!コンサートが近づいてきて、それまでなかった打楽器なんかが参加して初めて合わせたときの、あの震えるような感動・・・・・・鳥肌が立つような瞬間ったらない」(竹内さん)〉(『親子で奏でるアンサンブル』より)
日本での大学時代の4年間は、本当にどっぷりオーケストラ活動に浸かった。あんな時間はもう二度と持てないだろう。当時の仲間の近況をSNSなどで読み知ると、今も会社員や主婦をしながら複数のアマオケを掛け持ちしている人もいれば、きっぱりやめてしまった人もいる。その両方の気持ちが何となくわかる。このデジタル時代においても、オーケストラでは数十人、ときには100人近いメンバーが集まらないことには基本的に練習が始まらない。娯楽にあふれ、スケジュールが過密な現代社会において、これはなかなか大変なことだ。もちろんお金だって結構かかる。私の場合は、ベルリンのアマオケでも演奏する機会を得たことで、また別の角度から音楽に触れる楽しみを味わうことができた。日独のアマチュアオケを比較してみて思うのは、日本のアマオケのレベルや広がり方は、なかなかすごいものではないかということだ。弦楽器のレベルは総じて高いし(おそらくドイツよりも)、マーラーやブルックナーの大曲に挑む団体だって少なくない。そういえば昨年、世界的に活躍する指揮者の友人がこんなことを言っていた。「例えば東京には、山手線の駅ごとにアマチュアオーケストラがあるでしょ。そんな国は日本だけ」と。
アマチュアオケや吹奏楽に親しんでいる人口がこれだけいる。毎年12月になると全国津々浦々でベートーヴェンの第9が奏でられる。海外から来日する一流楽団やソリストの数は相変わらずだし、時々著名アーティストにインタビューをすると、誰もが例外なく日本の聴衆のことを絶賛する。なのに、それらが文化としての豊かさに今ひとつつながっていないと感じられてしまうのはなぜなのだろうか。作家の赤川次郎さんのエッセイ『オーケストラは生きている』の中に、こういう箇所があった。
〈しかし、その一方でプロのオーケストラはどこも大変だ。大阪のように、音楽に全く理解のない市長の下、わずかな補助金も打ち切られ、解散の危機に追い込まれている所もある。
もともと日本の、文化にかける予算の乏しさはとても先進国と言えない状況である。
世界の一流国と言うなら、防衛庁を防衛省にするより、文化庁を文化省にするのが先だろう〉
作曲家の久石譲さんのインタビューも、オーケストラの未来を考える上で示唆に富んでいる。
〈最終的に僕が言いたいことは一点。クラシックが古典芸能になりつつあることへの危機感です。そうでなくするにはどうしたらいいかというと、”今日の音楽”をきちんと演奏することなのです。昔のものだけでなく、今日のもの。それをしなかったら、十年後、二十年後に何も残らない。
(略)
ところが、過当競争の中にある日本の指揮者は実験できないのです。多くのオーケストラが公益法人になって赤字を出すことが許されない中で、集客できる古典ばかりを演奏することになる。
(略)
もちろん、僕がかかわる新日本フィルハーモニー交響楽団をはじめ意欲的に取り組んでいる楽団はあります。だがトータルで言うと、”今日性”につなげる努力はものすごく少ない。このままだと、先細りすると心配しています。オーケストラのあり方を考えるのは、日本の音楽、文化としての音楽について考えることと一緒だと思うのです〉
ところで、冒頭の思い出話を書こうと思ったのは、千葉県の少年少女オーケストラを長年指導されてきた佐治薫子さんのインタビューを読んでいたときだった。ここに紹介されている、佐治先生が指導されてきた学校のひとつ「市川市立鬼高小学校」という名前には記憶がある。私が小学6年の時に聴いた「あの忘れがたき」2つの《新世界》うち、どちらかを佐治先生が指揮されていた可能性はかなり高い。
〈小学生が交響詩『フィンランディア』や『エグモント』序曲を演奏するのがすごいとよく言われますが、難しい曲を上手に弾けるかどうかよりも、日々の練習の過程が大事。結果はあとからついてくるものです。楽しくないところに子供は来ない。合奏クラブに行けば毎日楽しいと思わせることが何より大事なのです。
それから良い演奏にたくさん触れさせる。自分もこんないい音を出したいと思わせる。ベートーベンの『運命』を鑑賞するのに大人も子供も関係ないのです〉
レベルの差はあれど、自分で楽器を持って、オーケストラの中で音を奏でる。そこで学べる大きなこと、これは他の芸術ジャンルについても当てはまることだと思うが、人や文化の多様性であり、「共に生きること」そのものではないかという気がする。今回の特集で私はベルリン・フィルの教育プログラムについて書かせていただいたが、取材中にもそのことを強く感じた。振り返ってみると、4年間大学のオケで活動していても、(大所帯だったこともあって)会話らしい会話をしないまま卒業してしまった仲間もいる。いろいろな考えの人が集まっているから、中には「アイツは気に入らない」ということだってあるだろう。だが、例えばホルンがメロディを奏でているときは、全員で耳を澄ませて一生懸命それに合わせる。そこからベートーヴェンならベートーヴェンの音楽が、意志を持って沸き上がってくる。指揮者グスターボ・ドゥダメルの冒頭のインタビューの言葉を借りれば、「すべては音楽への”奉仕”である」。ここにこそ、オーケストラが持つ力とかけがえのなさがあるように思うのだが。
〈オーケストラはコミュニティであり、社会です。すべてにおいて最も大切なのはハーモニー。それは音楽的、技術的なハーモニーだけでなく、共に生きるという意味でのハーモニー。音楽が創り出すのはまさにそのハーモニーであり、時には社会が見失いがちだけど、いちばん大切なものなのです〉(『グスターボ・ドゥダメル インタビュー』より)