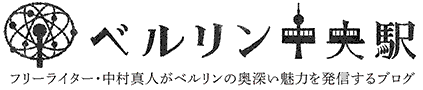コンツェルトハウスでの自分たちの演奏会がいよいよ今晩(5日)に迫った。アマチュア音楽家として、幸運なことに今までいろいろな曲と直に触れることができ、貴重な経験をさせてもらってきたけれど、今回のグスタフ・マーラーの交響曲第2番《復活》は、その中でも際立ったスケールと内容の深さを持つ作品の一つであることに間違いない。かれこれ3ヶ月この大曲と付き合ってきたので、「今日でもう終わりか」という名残惜しい気持ちがある一方、不安を抱えたまま臨まなければならない箇所もあって、なんだかいつになくソワソワしているのが正直なところ。この数ヶ月を振り返って、《復活》とのあれこれを思いつくままに綴ってみたいと思う。

そもそもアマチュアのオーケストラがなぜこんな大曲に挑むことになったかというと、2年半前からメンバーに入れてもらっているオーケストラ(Junges Orchester der FU)の創立20周年の記念公演の演目に選ばれたから。ベートーヴェンの第9やベルリオーズの幻想交響曲なども演目の候補に上がったらしいのだけれど、指揮者の強い意向などもあってマーラーの《復活》に決まったらしい。この作品は、大編成のオーケストラに加え、合唱、ソプラノとメゾソプラノのソリスト、さらに金管楽器の別働隊(バンダ)も要するとあって、プロのオーケストラでもそうそうは取り上げられない。ましてや、アマチュアではなおさらのこと。今回の合唱団は3つの団体からなる混合(そのうち一つはドレスデンから参加)で、ソリストにはベルリン国立歌劇場の若手歌手が駆けつけてくださった。演奏者が総勢何人になるのかはわからないが、よくぞこれだけの人々が集まったものだと思う。
3ヶ月練習してきた中で、とりわけ印象に残っている瞬間がいくつかある。一つは、1月初頭の週末、オーケストラの合宿に参加し、集中的にリハーサルをしたときのことだ。場所はメクレンブルク州の田舎街ブルク・シュターガルトのユースホステル。正直、私はこのとき気分があまり優れなかった。自分の中に潜んでいるネガティブな感情が吹き出していたというか、なんだかやたらと悲観的なことばかり考えていたのだ。そんな中、日曜の午後、最後の通し練習が行われた。《復活》を最初から最後まで通して演奏するのは、このときが初めてだった(演奏時間は80分にも及ぶ)。第5楽章の途中まで、比較的冷静な気持ちで吹いていたのだが、本来合唱が加わって感興が頂点に達するあの箇所で、私は電流に打たれたように感動してしまったのだ。そのときはオーケストラだけの演奏だったにも関わらず。
Sterben werd ich, um zu leben!
私は生きるために死のう!
Auferstehn, ja auferstehn wirst du,
よみがえる、そうだ、おまえはよみがえるだろう、
mein Herz, in einem Nu!
わが心よ、ただちに!
この日の午後、雲の動きが早く、空は刻々とその色合いを変えていた。そして、これは単に私の勝手な思い違いである可能性が高いのだが、記憶の中では、この箇所に差し掛かったあたりで、窓から光が差し込んで、指揮者にまさに後光が射したように見えたのだ。練習が終わると、不思議なことに、私の中のネガティブな感情はさっぱり消えていた。宿を出た時、肌に当たる冷気が清々しく、帰りの車の中から眺めるメクレンブルク州の田舎の風景は、何もかもが美しく見えた。あのときの幸福な気持ちは、その後も1週間ぐらい続いたのだ。
そして、もう1つはつい数日前、最初の本番の会場であるゲッセマネ教会でのプローベのこと。それまでずっとオーケストラだけで練習をしてきて、この日初めて合唱とソリストを交えてリハーサルをしたのだった。「よみがえる、そうだ、おまえはよみがえるだろう」の合奏の導入が自分のすぐ後ろからピアニシモで聴こえてきたときは、人間の声の持つ力というものにじんときた。ソプラノ独唱が「おお、信じよ、おまえは空しく生まれたのではない!」と歌いだし、やがてアルト独唱と力強い掛け合いになるところでは、「ああ、ひょっとしたら自分は、この時間を味わうためにドイツに来たのではないだろうか」などと思ってしまったほどだった。
そもそも、マーラーが作曲した《復活》が史上初めて音として立ち現れたのは、ベルリンにおいてだった。1895年12月13日、マーラーは私財を投じてベルリン・フィルや合唱団、ソリストを雇い、全曲の初演にこぎ着けたのだそうだ。当時マーラーのアシスタントだったブルーノ・ワルターがこの場に居合わせ、感動的な回想録を残している。
実際この演奏会の圧倒的印象は、私の回想の中で、最もすばらしいもののひとつなのである。私は、終楽章の偉大なるラッパで世の終わりを告げた後に、復活の神秘的な鳥の歌を聴いた時の息もつけぬような緊張感、それに続く合唱「よみがらん汝は」も導入される部分における深い感激を今でもはっきり耳にすることができる。もちろんそこには、反対者があり、誤解があり、軽蔑があり、冷笑があった。しかしその作品の壮大なこと、独創的なこと、かれの個性の強力なことの印象の方が余りにも深く大きかったので、その日から、マーラーは、作曲家として、最高の地位をもって迎えられるようになったのであった。
(ブルーノ・ワルター『マーラー 人と芸術』(音楽之友社より)
 今回ピッコロと3番フルートのパートを受け持つ私が特に緊張しそうなのが、ワルターのこの回想録にある「復活の神秘的な鳥の歌」の箇所だ。マーラーが「最後の審判」を描いたとされる管弦楽の咆哮が頂点に達した後、突如静寂が訪れ、舞台裏のホルンがこだまのようなエコーを奏でる。そして、フルートとピッコロが鳥の音を奏で始める。同じ鳥でも、ベートーヴェンの《田園》やマーラーの《巨人》に出てくる明朗なカッコウなどと違って、夜の暗闇の中から夜鶯の音が密やかに聞こえてくる感じだ。舞台裏のトランペットとも音が交錯するこの箇所、練習で合わせる回数が少なかったこともあって(言い訳になるが)、不安なまま本番に臨むことになってしまった。本物の鳥のように無心で奏でられたらなあ、と思う。
今回ピッコロと3番フルートのパートを受け持つ私が特に緊張しそうなのが、ワルターのこの回想録にある「復活の神秘的な鳥の歌」の箇所だ。マーラーが「最後の審判」を描いたとされる管弦楽の咆哮が頂点に達した後、突如静寂が訪れ、舞台裏のホルンがこだまのようなエコーを奏でる。そして、フルートとピッコロが鳥の音を奏で始める。同じ鳥でも、ベートーヴェンの《田園》やマーラーの《巨人》に出てくる明朗なカッコウなどと違って、夜の暗闇の中から夜鶯の音が密やかに聞こえてくる感じだ。舞台裏のトランペットとも音が交錯するこの箇所、練習で合わせる回数が少なかったこともあって(言い訳になるが)、不安なまま本番に臨むことになってしまった。本物の鳥のように無心で奏でられたらなあ、と思う。
もう一つ、いつも興味深く拝見している音楽ジャーナリスト、林田直樹さんのLinden日記(2013年11月2日)から引用させていただく。その少し前に横浜で行われたインバル指揮東京都交響楽団のマーラーの交響曲第6番の演奏会について、林田さんが書かれた文章だ。
第1楽章や第3楽章アンダンテにも出てくるカウベル(牛の首につける鈴)の音響的効果は、個人的に大好きなところ。今回の演奏を聴きながら改めて思ったのは、マーラーの交響曲の中に、避けがたく動物の雰囲気が入ってくるということの魅力である。
マーラーが人生を語ろうとするときに、そこに動物や鳥や虫たちや、山岳地帯の草原や青空や陽光が必ず混入してくるような、そういう世界観のあり方じたいが、素晴らしいと思うのである。「自然がなければ人は生きられない」ということを、マーラーの交響曲ほど身を持って感じさせてくれるものはない。
都会にいながらにして、自然の空気をたっぷりと吸い、草の中に寝転んで、のどかな牛たちの雰囲気を感じながら、一時的に去って行った人生の闘争から離れ、つかの間の安堵の時間を過ごす――あのアンダンテが連れて行ってくれる世界は、本当にかけがえがない。
《復活》にカウベルは登場しないけれど、私もこの曲のあらゆる楽章で、自然の情景や田舎のあぜ道がふと脳裏に浮かぶ瞬間がある。あのときのメクレンブルク州の田園風景も。
最近《復活》の中に登場する楽器で気になるのは、ルーテと呼ばれる硬いブラシ状の桴(ばち)の一種だ。マーラーがどういう意図でこの楽器を使ったのかはわからないけれど、私には、第3楽章でこのルーテが後ろでゴソゴソやったり跳ねたりしているのが虫の音に聞こえて仕方ない。
 この雑文の最後に、小澤征爾さんと村上春樹さんの対談本『小澤征爾さんと、音楽について話をする』(新潮社)の中で、小澤さんがマーラーの音楽について率直に語っている言葉を抜き出して、今夜本番に臨む仲間と自分自身への励まし(?)としたい。
この雑文の最後に、小澤征爾さんと村上春樹さんの対談本『小澤征爾さんと、音楽について話をする』(新潮社)の中で、小澤さんがマーラーの音楽について率直に語っている言葉を抜き出して、今夜本番に臨む仲間と自分自身への励まし(?)としたい。
小澤 結局ね、マーラーってすごく複雑に書いてあるように見えるし、またたしかに実際にオーケストラにとってはずいぶん複雑に書いてあるんだけど、でもマーラーの音楽の本質っていうのはね—こういうものの言い方をすると誤解されそうで怖いんだけど—気持ちさえ入っていけば、相当に単純なものなんです。単純っていうか、フォークソングみたいな音楽性、みんなが口ずさめるような音楽性、そういうところをうんと優れた技術と音色をもって、気持ちを込めてやれば、ちゃんとうまくいくんじゃないかと、最近はそう考えるようになりました。
村上 うーん、でもそれって、口で言うと簡単だけど、実際にはすごく難しいことじゃないんですか?
小澤 うん。もちろんそりゃ難しいんだけど……あのね、僕が言いたいのは、マーラーの音楽って一見して難しく見えるんだけど、また実際に難しいんだけど、中をしっかり読み込んでいくと、いったん気持ちが入りさえすれば、そんなにこんがらがった、わけのわからない音楽じゃないんだということです。ただそれがいくつも重なってきていて、いろんな要素が同時に出てきたりするもんだから、結果的に複雑に聞こえちゃうんです。
(『小澤征爾さんと、音楽について話をする』(新潮社)より)
小澤さんが言うところの「うんと優れた技術と音色」は、アマチュアの僕らは残念ながら持ち合わせていないけれど、少なくとも精一杯の気持ちを込めて、この高い峰のような作品に挑みたいと思う。