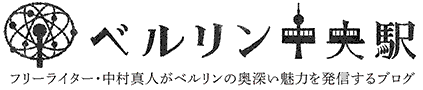今年のベルリン音楽祭Musikfestでは、音楽における政治性というテーマからショスタコーヴィチが大きな柱に選ばれていました。これは今年の壁崩壊20周年、すなわち東欧諸国における共産主義支配からの解放という出来事と大きな関わりがあります。いくつか足を運んだ中から、衝撃的なまでに素晴らしいコンサートに2つ出会いました。
今年のベルリン音楽祭Musikfestでは、音楽における政治性というテーマからショスタコーヴィチが大きな柱に選ばれていました。これは今年の壁崩壊20周年、すなわち東欧諸国における共産主義支配からの解放という出来事と大きな関わりがあります。いくつか足を運んだ中から、衝撃的なまでに素晴らしいコンサートに2つ出会いました。
1つ目はラトル指揮ベルリン・フィルによるショスタコーヴィチの交響曲第4番。
この音楽を生で聴いて、私は心底打ちのめされました。マチネーのコンサートだったにも関わらず、その日はどこか興奮状態で夜もなかなか寝付けなかったほどです(笑)。今までいろいろなシンフォニーを聴いてきましたが、この大曲をこの見事な演奏で聴いたことは私の交響曲体験において1つの「事件」ともいえる出来事でした。
何といってもこんなすごい曲があったのかという驚き。不覚にも私はこの交響曲4番が生まれた背景をほとんど知りませんでした(2003年にゲルギエフの指揮で一度だけ聴いたことがありますが、その時も圧倒されたもののその後CDで聴くことはほとんどなかったんです)。1935年から36年にかけて作曲されたので、ショスタコーヴィチが29歳かそこらで書き上げたということ、そして当局から消されるのを恐れて、完成から1961年の初演まで25年間も「封印」されていたという事実に、まず関心が向います。
ブラームスの1番が「ベートーヴェンの10番」と言われるように、私はショスタコーヴィチのこの交響曲を「マーラーの11番」というように思っています。マーラーの生まれ変わりがロシアに現れて、20歳台で才気溢れる大交響曲を作曲した・・・ しかし、その時、国家はソビエトに変わっていたので、初演が行われないまま、約30年間も演奏が禁止された。
私の親しい知人がこのように語っていましたが、ラトル&ベルリン・フィルの演奏を聴いた後ではそれもむべなるかなと思わされます。2楽章のいかにもマーラー風のレントは、まだ流れがつかみやすいのですが、約30分の長大な両端楽章については、一体どう表現すればいいのか・・・
プログラムの解説によると、ショスタコーヴィチはこの4番を自分の最高のシンフォニーと語っていたのだそう。私は15曲全部をしっかり聴いたわけではないですが、少なくともこの4番以上に思いのたけを音で表現したと感じられる曲に出会ったことがありません。音楽の大胆な展開と激烈なエネルギーに何度ものけぞりそうになりながらも、精緻で詞的な部分においても魅力に事欠きません。3楽章冒頭の悲歌と独自の諧謔味。そして、時おり浮かび上がってくる美しいソロの数々。特にエキストラのメンバーらしかったファゴットの名手を初め、トロンボーンやイングリッシュホルンなど、実にすばらしかった。まあ、フル編成の弦はもちろん、あれだけの数の管打楽器が並ぶ様は壮観で、冒頭からフィナーレの最後に出現する金管の咆哮まで、すごい迫力でした。
今回の4番をベルリン・フィルが取り上げるのは12年ぶりだったとか。生で聴けて幸運でした。今晩ベルリンの東の郊外、ケペニックの元工場で演奏された後、短期間のツアーに持っていかれるそうです。その最後の公演地がワルシャワだそうで、かの地の人々はこの曲をどういう気持ちで聴くのだろうかとふと思いました。
2つ目はネルソンス指揮バーミンガム市響の6番を中心としたプログラムです。2007年にこの指揮者を初めて聴いて以来注目していたのですが、いつの間にバーミンガムのシェフになり、来年はバイロイト・デビューを果たすそうですから、大変な勢いを感じます。この日は、ブリテンの『4つの海の間奏曲』、TurnageのFrom the Wreckageと、ショスタコのジャズ組曲第1番というジャズの影響を濃厚に受けた2曲の後、ショスタコーヴィチの6番の交響曲という、ラトルの時とはうって変わって全体的に明るくカラフルなプログラム。最初から最後までネルソンスの指揮に釘付けでした。この人の棒にかかると、とにかく音楽が生気に富み、響きが立体的になります。決して勢いだけで盛り上げるというわけでもなく、演奏者も聴き手もいつの間にか魔法にかけられていて、心地よくボルテージが上がっていく感じです。バーミンガム市響との相性はとてもよさそうでした。
この秋はショスタコーヴィチをいろいろ聴いてみようと思いました。